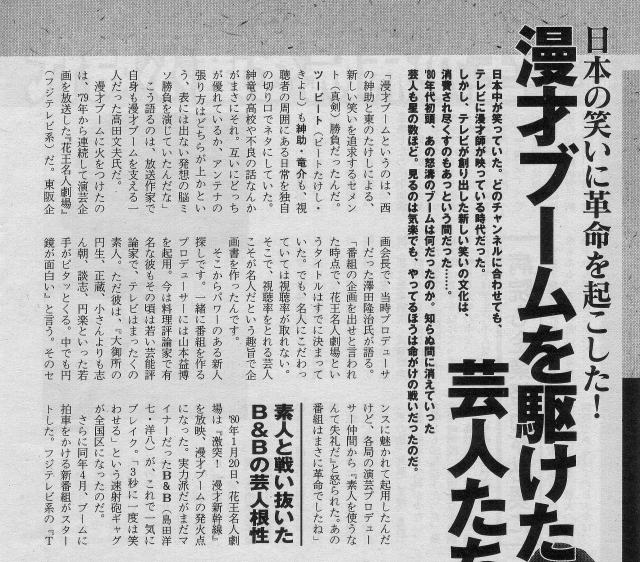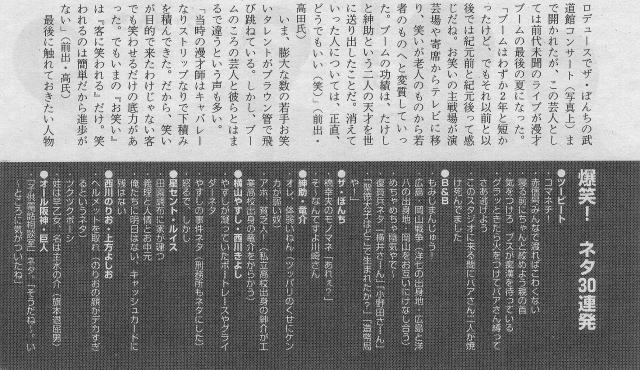| �i��̋L���̃e�L�X�g�j |
|
|
�N���u�T���i�T������@2004.4.24�j
�T�����[�}���̕��ی�@��16��
���{�̏��Ɋv�����N�������I
���˃u�[�����삯���|�l����
���{�������Ă����B�ǂ̃`�����l���ɍ����Ă��A�e���r�ɖ��ˎt���f���Ă��鎞�ゾ�����B
�������e���r���n��o�����V�������̕����́A�����s�����̂������Ƃ����Ԃ������E�E�E�B
'80�N�㏉���A���̓{���̃u�[���͂Ȃ����̂��B�m��ʊԂɏ����Ă������|�l�����̐��قǁB������̂͋C�y�ł��A����Ă�ق��͖������̐킢�������̂��B
�u���˃u�[���Ƃ����̂́A���̐a���Ɠ��̂������ɂ��A�V��������Njy����Z�����g�i�^���j�����������B
�c�[�r�[�g�i�r�[�g�������E���悵�j���a���E������A�����҂̎��͂ɂ�������Ǝ��̐���Ńl�^�ɂ��Ă����B�a���̍��Z��s�ǂ̘b�Ȃ��܂��ɂ���B�݂��ɂǂ������D��Ă��邩�A�A���e�i�̒�����͂ǂ��炪�ォ�Ƃ����A�\�ɂ͏o�Ȃ����z�̔]�~�\�����������Ă����ȁv
�������̂́A������ƂŎ��g�����˃u�[�����x�����l���������c���v�����B
���˃u�[���ɉ������̂́A'79�N����A�����ĉ��|������������w�ԉ����l����x�i�t�W�e���r�n�j���B |
|
�������ŁA�����v���f���[�T�[�������V�c�����������B
�u�ԑg�̊����o���Ƃ���ꂽ���_�ŁA�ԉ����l����Ƃ����^�C�g���͂��łɌ����Ă����B�ł��A���l�ɂ�������Ă��Ă͎����������Ȃ��B�����ŁA������������|�l���������l���Ƃ�����|�Ŋ�揑���������ł��B
��������p���[�̂���V�l�T���ł��B�ꏏ�ɔԑg�����v���f���[�T�[�ɂ͎R�{�v�����N�p�B���͗����]�_�ƂŗL���Ȕނ����̍��͎Ⴂ�|�\�]�_�ƂŁA�e���r�͂܂������̑f�l�B�����ނ́A�w��䏊�̉~���A�����A����������u�A�k�u�A�~�y�Ƃ�������肪�s�^�b�Ƃ���B�Ȃ��ł��~�����ʔ����x�ƌ����B
���̃Z���X�ɖ�����ċN�p�������ǁA�e�ǂ̉��|�v���f���[�T�[���Ԃ���A�w�f�l���g���Ȃ�Ď��炾�x�Ɠ{��ꂽ�B���̔ԑg�͂܂��Ɋv���ł����ˁv
�f�l�Ɛ킢������B&B�̌|�l����
'80�N1��20���A�ԉ����l����́w���ˁI�@���ːV�����x����f�A���˃u�[���̔��Γ_�ƂȂ����B���͔h�����܂��}�C�i�[������B&B�i���c�m���E�m���j���A����ň�C�Ƀu���C�N�B�u3�b��1�x�͏킹��v�Ƃ������˖C�M���O���S����ɂȂ����̂��B
����ɓ��N4���A�u�[���ɔ��Ԃ�������V�ԑg���X�^�[�g�����B�t�W�e���r�n�́wTHE MANZAI�x���B�����`�[�t�f�B���N�^�[�����������`�a�����U��Ԃ�B
|
|
|
�u�_�����N��w�́A������x�A�m�I�Șb��ɂ����Ă����18����22�̑�w���B�X�^�W�I�̋q��7��3�ŏ����𑽂����Z�b�g����������THE MANZAI�ɂ��āA�Z�{������̟������p�u���Ȃł���Ă�݂����Ȋ����ɂ��܂����B�F���E���|��ڎw������ł��v
�o���҂͎��ɍi�����B�����̐��Z���g�E���C�X�A�c�[�r�[�g�A��ォ�瓌���ɍU�ߍ���ł���B&B�A�g�{���Ƃ̐a���E����A�U�E�ڂ炪�����܂��l�C�҂ɂȂ��Ă��������A�Ȃ��ł��擪��˂��������̂�B&B���B
B&B���g�{����ˍ莖�����ɈڐЂ����̂�'79�N9���B�ꔭ������q���Ă̏㋞�����������킯�����A�w�i�ɂ͂����܂����܂ł̌|�l�����ƃo�C�^���e�B���������B
'80�N4���ɂ́wTHE MANZAI�x�Ɠ����ɓ��{�e���r�n�w�����X�^�[�a��!!�x���X�^�[�g���Ă���B�v���A�}��킸�̂�������������ŁA�R���b�P��C�b�Z�[���`�Ȃǂ�y�o�����`���̔ԑg�����AB&B�͂Ȃ�Ƒf�l��}�C�i�[�|�l�ɂ܂����ĉʊ��Ƀ`�������W�����̂ł���B
�c�[�r�[�g�A�a����15��0�̃R���r
�o�����ɂ�����������В��̐Ԕ����ꎁ�����B
�u���ʂ͒f�����ł���B���ێ��������́A�w���O���͂����X�^�[�ȂB�o��K�v�͂Ȃ��B�f�l�ɕ�������ǂ�����x�ƖҔ������B
�ł����c�m�����w������`�����X���Ǝv���Ă���Ă݂܂��x�ƈ��Ă��ꂽ�B�ޓ��̖��˂ɂ͈��|����܂����ˁB�܂��ɏ��́h�b�E�h�ł��B����͕����Ă����Ă�10�T���������Ǝv���Ă�����A�݂��Ə����������v
|
|
��̃l�^�����m�ɂȂ�܂ŁA���ʂ�3�����͂�����Ƃ����B���̐V�l�^��10�T�A���Ńe���r�ɂ̂���B�������A�f�l�ɕ����邩������Ȃ��Ƃ�����ςȃ��X�N�������B�����������łɔ������̂����R���B����ł��m���́A�u�v���͂���Ȃɖʔ������Ƃ������Ƃ��������Ă�����炦����Ȃ��́v�ƌ����Ď������В�����������B�V������������Ƃ��Ă̎������݂���B
B&B�̐擱�ŁA���˂͋�O�̃u�[���ɓ˓������BB&B��Ǒ����A�����ɒǂ��������̂̓c�[�r�[�g���B�u�[���ȑO�A�ނ�͉��x���ς��������܂���Ă����B�ꏊ�͎�薟�ˎt�̓o����Ƃ��Ēm����NHK�́w�V�l���˃R���N�[���x�B
�c�[�r�[�g��'76�N����3�N�A���Œ��킵���B���̃E�P�͊ԈႢ�Ȃ��ނ炪�_���g�c�B�����A�l�^�ɕi���Ȃ��Ƃ������R�ŗD���������Ă����B
�̂Ă�_����ΏE���_����B����ȃc�[�r�[�g�ɖڂ����A�����E���c�n��Łw�}���\�����˥�c�[�r�[�g��M���O�E�f�X�}�b�`�x�Ȃ郉�C�u���d�|�����̂�����Ƃ̍��M���Y���B'78�N11���̂��Ƃ��B
�u�l�^��S���Ȃ���2���ԂԂ��ʂ��ł�����B�e���r����Ȃ��̂Łw�C������A�u�X���s����҂��Ă���x�Ȃǂ̉ߌ��ȃl�^�������Ȃ����������A���̓o�J�E�P�B�e���r�W�҂�ҏW�҂ȂNjƊE�l�̒��ڂ��W�߂�悤�ɂȂ�����ł��v
���˃u�[���̒S���肽���̒��ł��A��͂肽�����Ɛa���̍˔\�͌��o���Ă����B
�u���̍��̖��˃R���r�͈�l�̓V�˂ƈ�l�̕��ʐl�̑g�����ŁA�V�˂Ɩ}�l�̔�d�͑��6��4���炢�B�ł��A�c�[ |
|
|
�r�[�g�Ɛa��������15��0���炢�������i�j�B�����͕����E�����悤�Ȃ���B�ł��A�u�[��������ƕ�����Ă����킯����Ȃ��B�^������������A�{�ԑO�݂͂�Ȉُ�ɐ_�o���ɂȂ��Ă��āA�������Ȃ��{�ԑO�͊y������o�悤�Ƃ��Ȃ������B���̃R���r���E�P�Ă�̂�����̂͌������Č����v�i�O�o���c���j
�wTHE MANZAI�x�ɏo���������Z���g�E���C�X���A�O�̖��ˎt�̏��ŋq�������܂킳���Ƃ����āA�����A�ϋq�����ւ��ĕʎB�肵���Ƃ����G�s�\�[�h������B�킪�܂܂Ƃ����킪�܂܂����A����قǂ܂łɃs���s���Ƃ����^�����������ł͍s���Ă����̂��B
���c�����瑶�݂̔�d��0���ƌ���ꂽ�r�[�g���悵�����A�ނɂ������͂���B�u�l�Ƃ��Ă��A���Ƃ�����3�p�^�[�����炢�H�v���Ă�����B���܂̃e���r�͂����Ƃ������Ƃ��l���g��Ȃ��B���̏ꂻ�̏�ŃE�P�邾���̌|�l���������Ə̂��Ă���Ă���B����ł��|�l�����Ƃ����C�T���Ȃ���v
�a���̑����̗����i���������j�͔ߎS���B�R���r������A���Ƃ̎��s�Ȃǂ�1��2000���~�̕�������Ď��Ȕj�Y�B���݂Ɏ����ẮA���̊��y�X�E�\�O�Ŗ��������ē����̌W��������Ă���B���̗��������B
�u�a���̖��˂͉����B�E�P��Ƃ������Ƃ�O��I�ɍl����^�C�v�ŁA�V�i���I��S�����A�A�h���u�I�Ȃ�����������B�s�[�N���̔N���H�@7000���~���炢���Ⴄ���ȁB���������߂�1���~�v���C���[�ɂȂ����Ƒ����ł�������₩��A���������ȁB���܁H�@������Ƃ��Ă��ȁv
|
|
�j�V�r�ȓV�ˉ��R�₷��
'80�N�ɉ��������˃u�[���͗��N�Ƀs�[�N���}���A���������������n�߂�B�������n�߂�B&B�ɑ����ăg�b�v�ɖ��o���U�E�ڂ��A���R�[�h�w���̂ڂV�[�g�x�ő�q�b�g�������̂����̔N�B7���ɂ��V�c�������v���f���[�X�ŃU�E�ڂ̕����كR���T�[�g�i�ʐ^��j�܂ŊJ���ꂽ���A���̌|�l�Ƃ��Ă͑O�㖢���̃��C�u�����˃u�[���̍Ō�̉ĂɂȂ����B
�u�u�[���͂킸��2�N�ƒZ���������ǁA�ł�����ȑO�ƈȌ�ł͋I���O�ƋI������Ċ������ˁB�����̎��ꂪ���|����Ȃ���e���r�Ɉڂ�A���V�l�̂��̂����҂̂��̂ւƕώ����Ă������B�u�[���̌��т́A�������Ɛa���Ƃ�����l�̓V�˂𐢂ɑ���o�������Ƃ��B�����Ă������l�ɂ��ẮA�����A�ǂ��ł������i�j�v�i�O�o�E���c���j
���ܖc��Ȑ��̎�肨���^�����g���u���E���ǂŔ�ђ��˂Ă���B�������A�u�[���̍��̌|�l�Ɣނ�Ƃ͂܂�ňႤ�Ƃ������������B
�u�����̖��ˎt�̓L���o���[�Ȃ�X�g���b�v�Ȃ�ʼn��ς݂�ς�ł����B������A���ړI�ŗ����킯����Ȃ��q�ł��킹�邾���̒�͂��������B�ł����܂́w�����x�́w�q�ɏ���x�����B����̂͊ȒP������i�����Ȃ��v�i�O�o�E�����j
�Ō�ɐG��Ă��������l��������B��������a���̏�̐���ɂ����A����ɔj�V�r�ȓV�˥���R�₷���ł���B
|
|
|
�u���w2�N���̎��Ƀ��W�I�̂����R���e�X�g�̗\�I�ɉ��債�Ă������A���̎��_�ł��łɓV�ˏ��N�������B���w���̂₷�����A��������̖��˃R���r�Ɂw������������Ⴄ���x�Ƌ����Ă�������v�i�O�o�E�V�c���j
20�N�ȏ�o�������܂��e���r�̎���邽������a��������A�����Ă������|�l�������B�����ł͋�����Ȃ��������˃u�[���̗����҂����ɂ܂Ƃ߂��B�ނ炨���|�l�������������ł������̂��A���̊v���E���˃u�[���������̂��B |
|
|
| ��TOP�֖߂� |